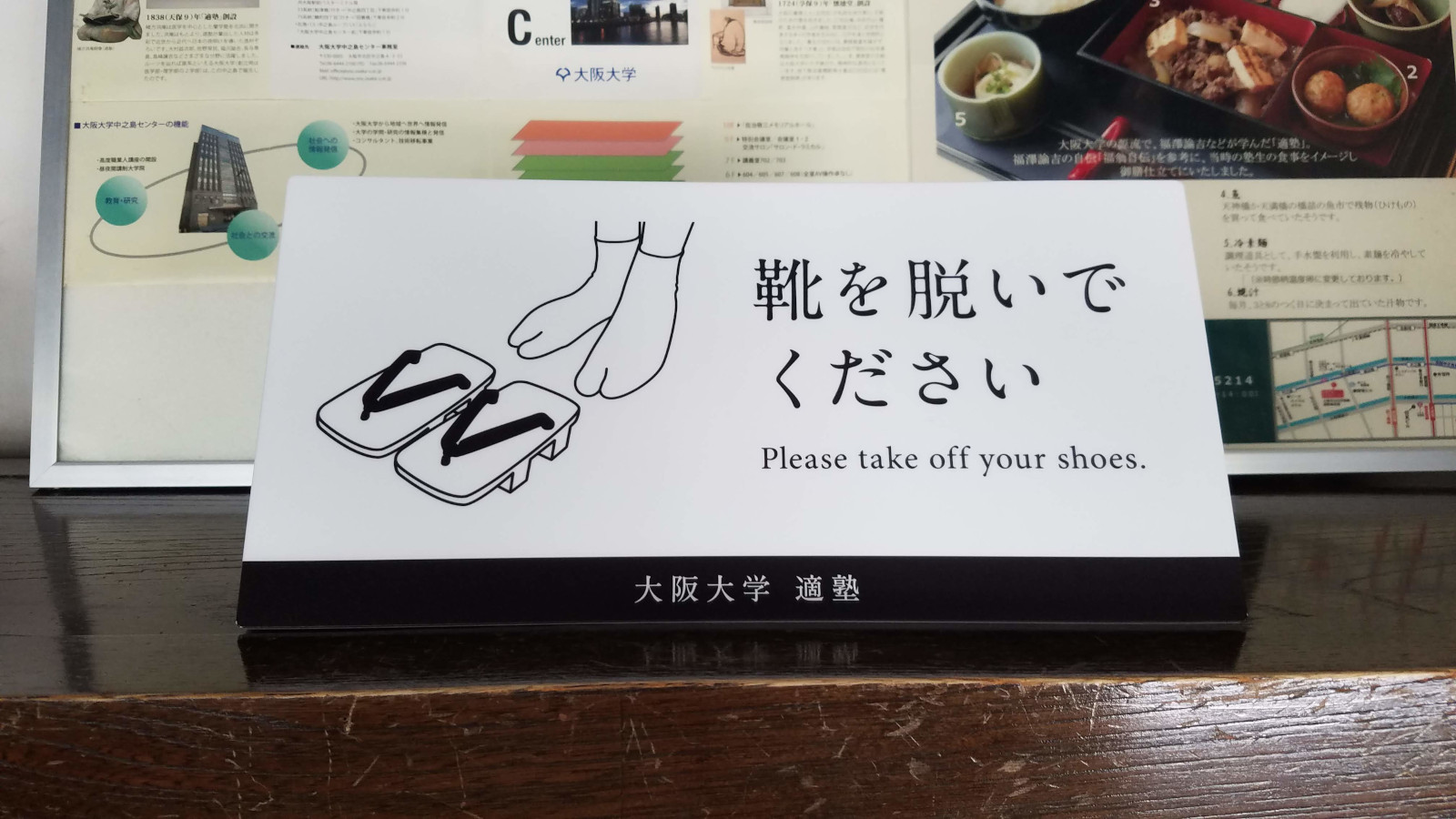『手の倫理』伊藤亜紗 https://bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000345814 という本を、以前購入していたのだけれど、先日、ちょっとしたきっかけがあって、改めて読み直してみた。
「ふれる」ことと「さわる」ことの違いとか、それぞれのあり方とか、そこにまつわる心の動きとか倫理的な問題とか、そういう話が山盛りになっていた。
彼女の説によると、「ふれる」ことは、お互いの相互関係を形成して、主体として「ふれる」ひともその経験から自分自身が変化する、と。
「さわる」というのは、わりと主客がはっきりしていて、主体はおおよそ変化しない、客体を評価する、的な枠組みを持つ言葉だ、って。
医療者っていうのは、患者である方の身体に「さわる」ことが多い、って書いておられた。うっかりそこで「ふれられる」なんてことがあっても困る、と。
もう一つ本からのエピソードを紹介しておこう。視覚障害者のマラソン、っていうのがあって、伴走者と一緒に走るのだけれど、その時に、誘導するために、紐でできたわっかを二人で持つ。で、それを紹介するために、持ってきた著者が、協力者に「こうやって持つんです」って共有したとたんに、相手の方がその紐を取り落とした?という話が書いてある。曰く、あまりにも伝わってくる情報量が多くて、この情報をそのまま受け取ってしまってはいけないのではないか、と感じて、とっさに手を離してしまったのだ、という。ふれる、ふれられる、ということの「危険性」を示唆しているエピソードだと、私は思う。
わたしは医療者で、かつ、産婦人科の仕事をしているから、プライベートな場所を拝見することもしばしば、ある。そういう場所の相談を頂いて、それにお返事するには、目で見るとか、さわる、ということが必要になることもあるから。職能的なものである。とはいえ、職能のかかわりであっても、最近はセクハラの問題がついてまわる。
先日、乳腺外科の先生が、術後の診察をしたときに、セクハラを受けた、という訴えをされて、裁判になっていた。議論としては、おそらく術後のせん妄だったんだろう、っていうことで、医師の行為には問題はなかった、って認定されるにいたったのだけれど、それまでにご家族が心労で大変なことになった、という話を伝え聞いている。
現代の日本では、さわる、とか、ふれる、ということがすごく減ってきているのだと思う。もう少し昔は当たり前にふれあっていたのだろうと思うのだけれど、いつの間に、こんなにも人との接触を忌避するようになってしまったのだろうか。
何もかも、あの米国の文化侵略が悪い、とは言わないのだけれど、欧米人は、シャワールームは個人の場所、らしいから、親子でお風呂に入る、なんていうのは、許しがたい行為だったのかもしれない。一方で、彼らはわりと積極的にハグをしたりする。
フィリピンの貧困の家庭では、そもそも寝る場所が狭い、っていうこともあるけれど、皆が折り重なって寝ているらしいから、人と触れているのが当たり前、だったりする。日本も昔はそうだったんだろうし、そういう空間から、自分自身のプライバシーが守れる場所、が確保された、っていうことはとっても大事なことだったんだろうと思う。の、だけれど、うまくいき過ぎた、のかもしれない。
ふれること、ふれられることっていうのは、ある種の「嫌なこと」が含まれる可能性とリスクにさらされ続けていて、それを上手いこと処理していくことが必要だったり、お互いに不快にならない方法を試行錯誤してみたり、っていう練習の場所だったのかもしれない。
そういう場所がなくなったことで、自分自身の安寧は得られたのだけれど、でも、それは、他者に触れられることをすべて拒絶してしまう、っていう、ヤマアラシのジレンマ的なさびしさにたどり着く結果だったのかもしれない。
自動締め付け器というのを考案した…というか、もともとウシを安定させるためにそのような器械があったらしいのだけれど、それをヒト用に作り直した…方がある。ご本人がアスペルガー症候群の方であったと記憶しているhttps://nihon-kyousou.jp/sfcc2018/proc/sfcc2018_A-10.pdf (『火星の人類学者』オリバーサックスhttps://www.hayakawa-online.co.jp/product/books/90251.html に紹介されていた。)たしか、彼女は、「ひとに抱っこされると暴れる」けれど、自分自身を覆って、輪郭がハッキリすることには安心感を得られる、っていうことで、この器械を自分用に準備した、とかそういう話になっていたように記憶している。
愛着形成っていうのは、皮膚感覚にけっこう依存する、っていう話は、ハーロウのアカゲザルの実験が有名だけれどhttps://s-counseling.com/harry-harrow/ アスペルガー症候群では、知覚過敏が出現していたりするから、だっこされる時に、安定感よりも、その違和感が強くでてしまっておられたのかもしれない。この器械が導入されることで、彼女はずいぶん気持ちが安定された、と書いてあった。
お化け屋敷なんかで、ヒトの形をしたお化けの怖いところは、目だったり、手だったりする。そういうものがうっかり視野に入ると、人はかなり、動揺することになるのだけれど、それは、まなざしや、手が「ふれてくる」存在だから、なのかもしれない。
医療の世界では、清潔操作というのがあって、患者さんに手術をするとか、あるいはカテーテルを入れるとか、っていうときには、術野を消毒する。消毒するだけじゃなくて、その周囲に覆布(おいふ)というものを掛けるのが一般的なやり方になっている。この覆布がかかることで、医者から見える皮膚が限定される。これは、相手を対象化する上ではとっても上手い方法なんだろうな、と思う。覆布によって輪郭を作られた、処置・手術する「対象」に視野を限定することで、私たちは、医療行為の引き起こす共感的な痛みから自分たちを遮断している、と言えるのかもしれない。
婦人科の内診台には、カーテンがある。このカーテンがかかっていて、医者と患者の顔があわないようにしてあるのも、欧米では一般的ではない、らしく、このカーテンにはそれぞれ賛否がある。が、それでも日本ではカーテンがあって、お互いの視線が重ならないようにしてある、っていうのは、診察という行為を対象化するための舞台装置であるように思われる。
一方で、対象化しすぎることで「モノ」扱いされてしまう、という問題点もある。
以前、聴診器やX線写真、遠隔医療などの医療機械の発明の歴史本(『診断術の歴史』https://www.heibonsha.co.jp/book/b159107.html )を読んでいたら、ことあるごとに「人間的な接触から遠ざかり、機械的な関わりになってしまった」って嘆きの文章が差し挟まれていた。聴診器なんて、今どきは、「医療現場における人間的な接触」のほぼ唯一とも言える場面じゃないの?なんて思うのだけれど、当時はそれすらも、器械が挟まることで、関わりがモノ的になる、っていう批判の対象になっていたらしい。日本語訳は1995年に出版されているのだけれど、原著は1978年らしい(翻訳出版まで15年以上かかっている!)から、まあ、論調が懐古主義的になるのも仕方ないのかもしれないけれど。
(なお、余談だけれど、この本の中には「幸いにも悪性の病変はなく、隣室で開かれた協議の結果、ソーダ水を数杯飲み、毎日乗馬するよう勧告することになった」という文章が出てくる。1870年代に書かれた「未来の医療」からの文章の引き写しではあるが、処方が「ソーダ水と乗馬」ってあたりが、本当に歴史を感じる。ソーダ水の処方箋はともかく、毎日乗馬の処方箋は引き受けてくれる薬局がみあたらない)
こういう「客観的な」情報が得られると、それが結構大きな「根拠」になったりはする。けれど、痛みには客観性は乏しいし、いわゆる不定愁訴ってやつも「客観的な」情報によって判定できないから「不定」なわけで、むしろ、患者を対象化して、客観性を重要視しすぎたことで、今の医療は患者のニーズとの間にギャップができてしまっている、とも言えるだろう(そもそも保険医療が、そのような患者のニーズに応えることをするべきかどうか、って話になると、もうひとつ面倒くさいから、そこはとりあえず考えないことにするけれど)。
CIVD-19っていう新興感染症が、パンデミックを引き起こしたことで、リモート面接、とかリモート会議っていうのが増えた。今までは移動の時間やコストをかけないと対話が難しかった相手と、わりと簡単に在宅で対話できるようになった、というのは本当に便利になったと思う。
一方で、直接会って、触れることの価値が相対的にとても高まったとも言える(加えて、難易度とか要求水準も上がったのかもしれない)。臨床っていうのが文字通り「床」に臨む、ということであれば、患者さんの横に立つことが、その原点ではあるはずで、医療者として、患者さんに触れる、っていうことは、いつまで経っても、医療の、あるいは人間と人間の関わりのなかにおける、ケアの根本的なモジュールの一つであるだろうと思っている。